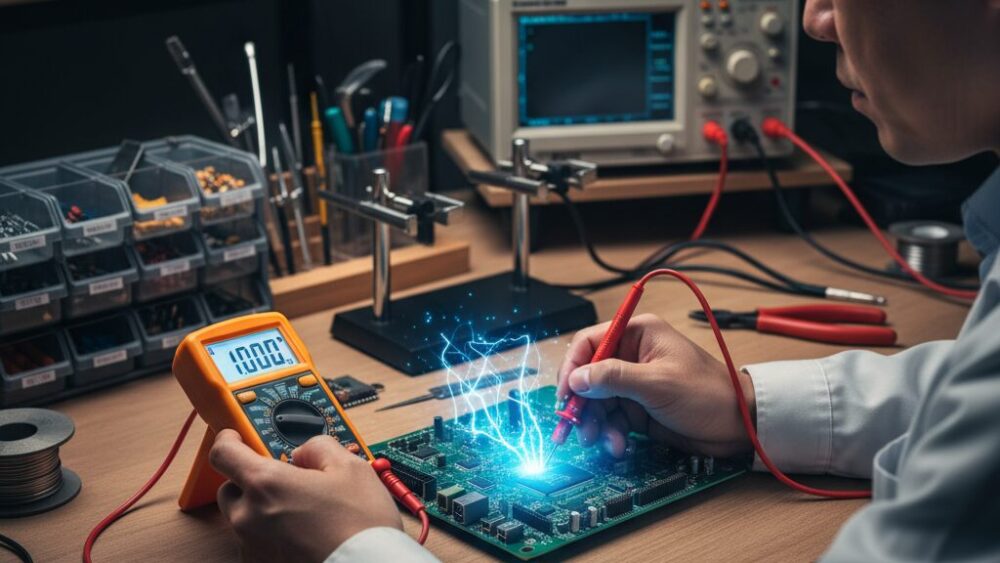プロフィール
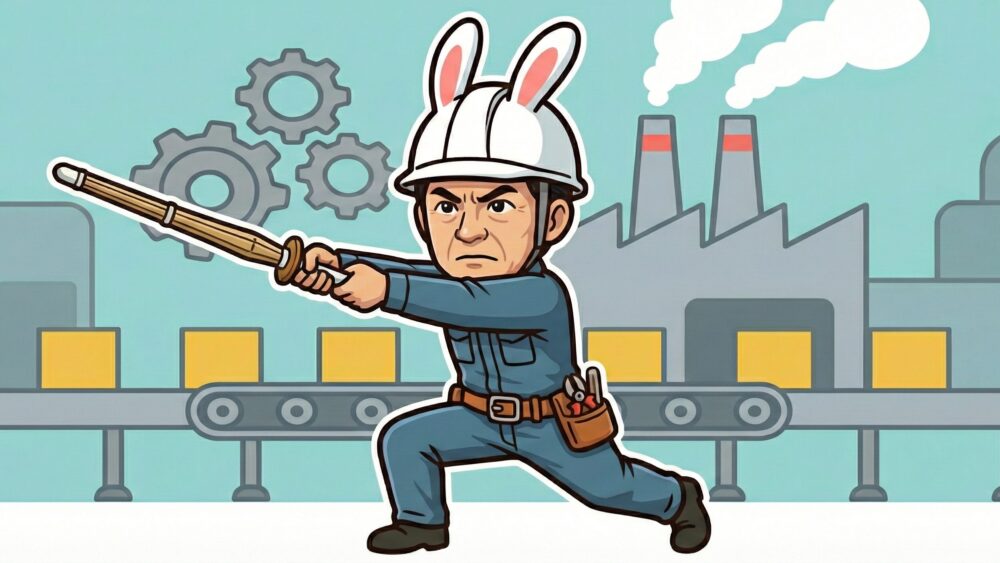
運営者プロフィール:機械の声を聞き、安全を刻む。
はじめまして。ハンド&パワーツール研究室 運営者の「機械の修理屋さんRABI」です。
本ブログは、単なる工具の紹介サイトではありません。機械修理歴40年の現場経験と第二種電気工事士の専門知識をベースに、剣道の精神に基づく安全哲学を融合させ、一生使える道具との出会いと怪我ゼロのDIYライフを提案するための研究所です。
世の中には星の数ほどの工具があふれていますが、その良し悪しを見抜くのは容易ではありません。私は40年間、産業用機械の修理現場に立ち続け、「なぜ機械は壊れるのか」「なぜこの工具は使いにくいのか」という問いと向き合い続けてきました。
壊れた機械は、嘘をつきません。摩耗したギア、焼き付いたベアリング、断線したコード。それらはすべて、設計の甘さや日常の整備の未熟さを物語っています。私の記事は、こうした故障品という動かぬ証拠から逆算して執筆しています。
また、DIYにおいて最も重要なのは、作品の完成ではなく無事に作業を終えることです。剣道の精神で学んだ残心(技を決めた後も油断せず相手を注視する心構え)は、電動工具や工作機械を扱う際にも共通する心理です。刃が当たる際の衝撃やスイッチを切った後の惰性で回る刃への警戒、作業環境を整える礼儀作法。これらはすべて、自分自身を守るための技術なのです。
当ブログでは、メーカーのカタログスペックだけでは見えてこない現場の真実を、忖度なしにお伝えします。プロの技術と精神を、あなたのDIYライフに応用していただくことが、私の最大の喜びです。
経歴・保有資格
| 項目 | 詳細内容 | ブログ記事への適用・強み |
| 職務経歴 | 機械修理・メンテナンス業(40年) 工場の産業用機械の修理業務に従事。 数千件に及ぶ故障事例の診断と復旧を担当。 | 「耐久性」の目利き 新品時の性能だけでなく、経年劣化のパターンを熟知。内部構造から各部の寿命を予測し、真にコストパフォーマンスの高い製品を推奨します。 |
| 保有資格 | 第二種電気工事士(国家資格) 電気設備技術基準に基づく配線工事、電気機器の設置に関する法的知識と技能を保有。 | 「安全性」の担保 コンセント増設やスイッチ交換など、法的に有資格者のみが許される作業範囲を明確化。テスター等の測定機器を用いた正しい電気診断法を解説します。 |
| 特技 | 剣道 初段 武道を通じた精神修養。 | 「安全管理」の哲学 「間合い(対象との距離感)」と「残心(作業後の警戒)」の概念をDIYに応用。電動工具による事故を防ぐための身体操作とメンタルセットを提唱します。 |
| DIY歴 | 自宅の家電、農機具の修理、電気配線整備など。 | プロ技術の翻訳 産業界の厳しい基準(JIS規格等)やプロの裏技を、一般家庭でのDIYレベルに落とし込み、分かりやすく解説します。 |
当ブログの運営方針と免責事項 (Policy & Disclaimer)
【電気工事に関する情報の取り扱いについて】 当ブログでは、第二種電気工事士である管理人が、自身の知識と経験に基づいて電気設備の仕組みや工具の使用法を解説しています。しかし、屋内配線の変更、コンセントの増設・交換など、電気工事士法で定められた「電気工事」に該当する作業を、無資格者が行うことは法律で固く禁じられています。
当ブログの記事は、電気の仕組みを理解し、安全意識を高めることを目的としており、無資格工事を推奨するものではありません。DIYにおける電気作業は、必ずご自身の保有資格の範囲内、または有資格者の監督下で行ってください。記事内の情報を参考にした作業によって発生した事故、火災、損害等について、当方は一切の責任を負いかねます。
【情報の客観性と広告について】 記事内で紹介する工具や機器は、管理人が実際に使用し、その性能を検証したものを中心としています。一部アフィリエイトリンクを含みますが、メーカーからの金銭授受による評価の改ざん(ステルスマーケティング)は一切行いません。「プロとして使えない」と判断したものは、その理由と共に率直に記載します。
お問い合わせ・訂正の受付
内容へのご意見・訂正依頼・取材依頼は、お問い合わせフォームからお願いします。事実誤認があれば迅速に調査・訂正します。
最後に
このサイトは、「まず安全、つぎに規格、最後に仕様確認」という迷わない順番で、はじめての方でも失敗しないDIYを目指しています。必要なときに、必要なだけ、一次情報へ。
今日の作業が、明日の自信につながりますように。
更新日
最終更新:2025年12月2日