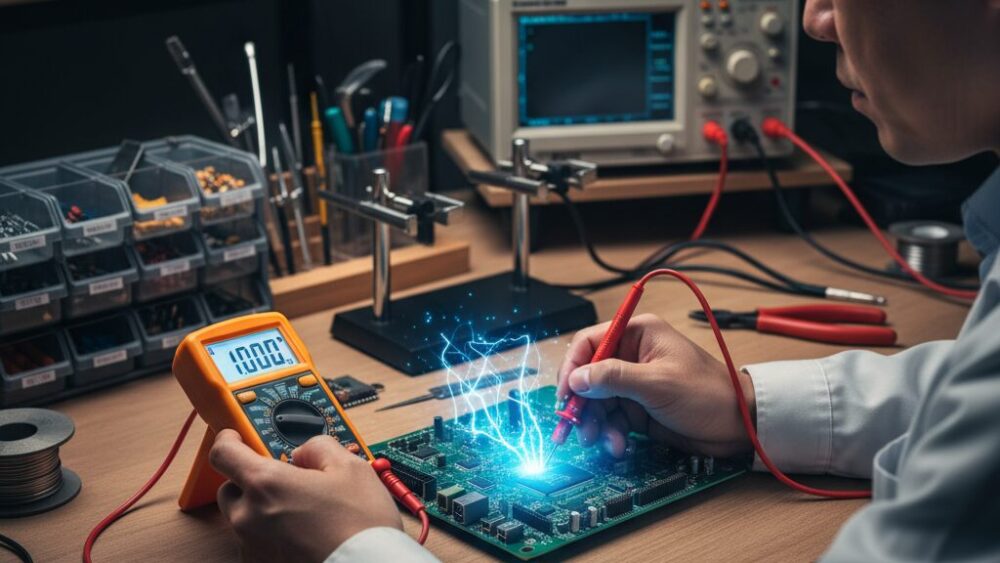初心者必見!DIY電動工具を揃える順番とコツ

DIYの世界へようこそ。
自分だけのおしゃれな棚を作ったり、古くなった家具をリメイクしたり、想像するだけでワクワクしますよね。
しかし、その第一歩として立ちはだかるのが「電動工具選び」の壁です。「一体どれから揃えればいいの?」「高価な買い物で失敗したくない」「そもそも、どんな種類があるのか分からない」…そんな不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事は、単なる工具のリストアップではありません。
DIY電動工具初心者が最初に知るべき事から、これだけは揃えたいDIY工具の必需品まで、あなたのDIYレベルや目的に合わせた「最適なロードマップ」を提示します。
まず、代表的な木工電動工具種類を解説し、あると便利な木材加工用工具一覧もご紹介。
さらに、一台で活躍する万能電動工具おすすめモデルの特徴や、おすすめDIY 電動工具セットの選び方のコツにも深く触れていきます。
人気のDIY 工具セットマキタ製品の強み、おしゃれなDIY 工具セット女子向けモデルの魅力、そして購入前に試すDIY 電動工具レンタルという賢い選択肢まで、あらゆる角度から徹底的に解説。
この記事を読み終える頃には、あなたに合うdiy 電動 工具の優先 順位が明確になり、自信を持って最適な一台を選べるようになっているはずです。
- 最初に揃えるべき電動工具がわかる
- 作業別の最適な工具の種類が理解できる
- セット商品やレンタルの賢い活用法がわかる
- 自分に合った工具選びの基準が見つかる
失敗しないdiy電動工具の優先順位と選び方

- DIY 電動工具初心者が最初に知るべき事
- これだけは揃えたいDIY工具の必需品
- 代表的な木工電動工具種類を解説
- あると便利な木材加工用工具一覧
- 一台で活躍する万能電動工具おすすめ
DIY 電動工具初心者が最初に知るべき事

DIYで電動工具を効率的に、そして無駄なく揃えるためには、最初に理解しておくべき普遍的な原則があります。
それは「締める・開ける→磨く→切る→加工する」という作業工程に基づいた優先順位です。
この順番を無視していきなり専門的な工具に手を出してしまうと、基本的な作業ができずに計画が頓挫してしまうことも少なくありません。
なぜこの順番が重要なのでしょうか。例えば、あなたが初めて「小さな本棚」を作るシーンを想像してみてください。
- 工程1:締める・開ける(組み立て) 設計図通りにカットされた木材を、ネジを使って組み立てていきます。この「ネジを締める」作業は、本棚の骨格を作る最も基本的な工程です。手動のドライバーでは何十本ものネジを締めるのは非常に時間がかかり、腕も疲れてしまいます。ここでドリルドライバーがあれば、作業は一瞬で完了します。
- 工程2:磨く(下地処理・仕上げ) 組み立てが終わった本棚の表面や角を滑らかにします。この「磨く」作業を丁寧に行うことで、手触りが良くなるだけでなく、塗装をする際の仕上がりが格段に美しくなります。手作業でも可能ですが、電動サンダーを使えば、均一でプロのような滑らかな表面を手間なく実現できます。
- 工程3:切る(材料の切り出し) DIYに慣れてきて、今度は自分で設計した通りのサイズに木材を切り出したくなりました。ここで初めて「切る」ための丸ノコやジグソーが必要になります。しかし、この工程はホームセンターのカットサービスを利用するという代替手段があるため、最初の段階では優先順位が下がります。
【ドリルドライバー】

【電動サンダー】

【丸のこ】

このように、DIYの基本的な流れに沿って、かつ手作業では代替が難しい、あるいは著しく効率が落ちる作業から電動化していくことが、最も合理的で失敗のない工具の揃え方と言えるのです。
DIYへの憧れから、見た目が格好良い「丸ノコ」を最初に購入してしまうケースです。
しかし、いざ木材をカットしても、それを組み立てるためのドリルドライバーがなければ、作品を形にすることができません。
まずはDIYの全工程を見渡し、最も頻繁に行う「組み立て」作業から効率化することを考えましょう。
これだけは揃えたいDIY工具の必需品

DIYの世界には数え切れないほどの電動工具が存在しますが、その中でも「これさえあれば、基本的なDIYは始められる」と言える、核となる必需品が2つあります。
それは、組み立ての要である「ドリルドライバー(またはインパクトドライバー)」と、仕上げの質を決定づける「電動サンダー」です。
ネジ締め・穴あけの主役:ドリルドライバー
ドリルドライバーは、その名の通り「ドリル(穴あけ)」と「ドライバー(ネジ締め)」の2つの機能を併せ持った、まさにDIYの基本中の基本となる電動工具です。
- トルク調整(クラッチ機能)の重要性 多くのドリルドライバーには、ネジを締める力を段階的に調整できる「トルク調整(クラッチ)機能」が搭載されています。これは非常に重要な機能で、例えば柔らかい木材に小さなネジを締める際にトルクを弱く設定すれば、ネジを締めすぎて木材が割れてしまったり、ネジ頭を潰してしまったりする「締めすぎ」を防ぐことができます。逆に、硬い木材に長いネジを打ち込む際はトルクを強く設定することで、パワー不足になることなく、しっかりと締め込めます。この繊細な力加減ができる点が、ドリルドライバーの大きな魅力です。
- 基本的なビットも揃えよう ドリルドライバーは、先端に取り付ける「ビット」を交換することで様々な作業に対応します。最低限、一般的なネジに対応する「プラスビット」の大小数種類と、ネジの下穴を開けるための「木工用ドリルビット」のセット(3mm〜6mm程度)を一緒に揃えておくと良いでしょう。
作品の質を高める:電動サンダー
電動サンダーは、木材の表面をサンドペーパーで高速に振動・回転させて研磨する工具です。
手作業に比べて圧倒的な時間短縮と、均一で美しい仕上がりを実現します。
- サンダーの種類と選び方 初心者におすすめなのは、パッドが細かく振動する「オービタルサンダー」か、振動しながら円運動もする「ランダムサンダー」です。オービタルサンダーは研磨力が比較的穏やかで扱いやすく、ランダムサンダーはよりパワフルでスピーディーに作業ができます。どちらもDIY用途では十分な性能を発揮しますが、汎用性の高さからランダムサンダーを選ぶ方が多い傾向にあります。
- サンドペーパーの番手を使い分ける サンダーの効果を最大限に引き出すには、サンドペーパーの「番手(目の粗さ)」を使い分けることが重要です。まずは中目(#120〜#180)で全体のざらつきを取り、次に細目(#240〜#400)で表面を滑らかに仕上げるのが基本です。このひと手間が、作品の完成度を劇的に向上させます。
【オービタルサンダー】

【ランダムサンダー】

研磨作業中は、目に見えないほどの細かい木の粉塵(ふんじん)が大量に発生します。
健康を守るためにも、必ず防塵マスクを着用しましょう。
また、サンダーに付属のダストバッグや、集塵機を接続することで、粉塵の飛散を大幅に抑えることができ、後片付けも楽になります。
代表的な木工電動工具種類を解説

DIYで活躍する主な電動工具には、それぞれに特有の機能と役割があります。
ここでは、基本的な6種類の電動工具をピックアップし、それぞれの主な用途、メリット、そして使用する上での注意点を詳しく比較解説します。
自分の作りたいものと照らし合わせながら、どの工具が次のステップとして必要になるかを見極めましょう。
| 電動工具の種類 | 主な用途 | メリット | デメリット・注意点 |
| ドリルドライバー | ネジ締め、小径の穴あけ | 精密な力加減(トルク調整)が可能、比較的静か | パワーが弱く、硬い材料や長いネジには不向きな場合がある |
| インパクトドライバー | 強力なネジ締め、穴あけ | 回転+打撃でパワフル、作業が速い、硬い材料にも対応 | 打撃音が大きい、繊細な力加減が難しく、ネジ頭を潰しやすい |
| 電動サンダー | 木材の研磨、表面仕上げ | 均一で滑らかな仕上がり、作業時間を大幅に短縮 | 機種により振動や音が大きい、粉塵対策が必須 |
| 丸ノコ | 木材の直線切断 | 高速かつ綺麗な切断面で切れる、厚い板も一度で切断可能 | キックバック(※)の危険性があり、安全な取り扱いには習熟が必要 |
| ジグソー | 木材の曲線切断、切り抜き | 曲線や複雑な形に切れる、刃が細く比較的安全性が高い | 直線切断の精度や速度は丸ノコに劣り、切断面が荒れやすい |
| トリマー | 面取り、溝掘り、飾り加工 | 作品の角を丸めるなど、仕上がりがプロ並みに向上、加工の幅が広がる | 使い方がやや複雑で、ビットなど付属品の知識も必要 |
トリマー】

※キックバック:切断中に刃が木材に挟まるなどして、工具本体が作業者側に激しく跳ね返ってくる危険な現象。
各工具のさらに詳しい解説
- インパクトドライバーのメカニズム インパクトドライバーは、回転方向に「打撃(インパクト)」を加えながらネジを締めるのが特徴です。一定以上の負荷がかかると内部のハンマーが作動し、金槌で叩くように瞬間的な力を加えることで、硬い木材にもパワフルにネジを打ち込むことができます。このため、ウッドデッキ作りなど、長いコーススレッドを多用する作業では絶大な威力を発揮します。
- 丸ノコの安全な使い方 丸ノコは非常に便利な反面、最も注意が必要な工具です。安全に使うためには、必ず両手でしっかりと本体を保持し、切断する材料はクランプなどで確実に固定することが鉄則です。また、最近のモデルには、スイッチを離すと刃の回転がすぐに止まる「ブレーキ機能」や、キックバックのリスクを軽減する「電子制御機能」が搭載されているものも多いので、初心者ほどこういった安全機能を重視して選ぶことをお勧めします。
- ジグソーの多様性 ジグソーの魅力は、ブレード(刃)を交換することで木材だけでなく、プラスチックや軟鉄板など様々な素材を切断できる点にあります。また、「オービタル機能」が付いているモデルは、ブレードが上下運動に加えて前後の振り子運動を行うことで、切断スピードを向上させることができます。ただし、切断面はやや荒くなる傾向があるため、仕上げの綺麗さを求める場合はオービタル機能をオフにして使用します。
- トリマーで広がる表現の世界 トリマーは、先端の「ビット」を交換することで、様々な形状の飾り面加工が可能になります。例えば、テーブルの天板の角を丸くする「ボーズ面ビット」や、アンティーク家具のような装飾的な縁取りができるビットなどがあります。最初は扱いが難しく感じるかもしれませんが、使いこなせるようになると、DIY作品の表現力が飛躍的に向上する、非常に奥の深い工具です。
あると便利な木材加工用工具一覧

ドリルドライバーやサンダーといった基本工具を揃え、DIYの楽しさと奥深さに目覚めたなら、次のステップとしてより専門的な加工用工具に目を向けてみましょう。
これらは必ずしも全員に必須ではありませんが、使いこなすことでDIYの可能性を大きく広げ、作品のクオリティをプロのレベルへと引き上げてくれる、頼もしい存在です。
電動カンナ:平面を極めるための道具
電動カンナは、高速回転する刃で木材の表面を薄く削り出し、平滑な面を作り出すための専門工具です。
手作業のカンナがけは、熟練の技術と経験がなければ難しい作業ですが、電動カンナはガイドを木材に沿わせて動かすだけで、比較的簡単に平面出しが可能です。
- 具体的な使用シーン
- 反りや歪みの修正: 購入した木材がわずかに反っていたり、湿度で歪んでしまったりした場合に、表面を削って平らに修正することができます。
- 古材の再生: 古い家具や柱の塗装・汚れを表面ごと削り取り、新しい美しい木肌を蘇らせることができます。
- 厚みの微調整:「あと1mmだけ板を薄くしたい」といった、設計上の精密な厚み調整を行いたい場合に活躍します。
選び方のポイントとしては、一度に削れる幅(切削幅)と、削る深さを調整できる機能(切削深さ)が挙げられます。
DIY用途であれば、切削幅が82mm程度の標準的なモデルで十分対応可能です。
【電動カンナ】

スライド丸ノコ:高精度な角度切断を実現
スライド丸ノコは、作業台に固定して使用する据え置き型の切断工具です。
手持ちの丸ノコがフリーハンドで切断するのに対し、スライド丸ノコは材料をしっかりと固定し、レールに沿ってノコ刃をスライドさせるため、極めて高い精度で直角や任意の角度に切断できるのが最大の特長です。
- 具体的な使用シーン
- 精密な直角切り: 本棚の棚板や箱物家具の側板など、正確な直角が求められる部材を、誤差なく切り出すことができます。
- 角度切り(留め切り): 額縁や窓枠のように、部材の端を45度でカットしてぴったりと合わせる「留め加工」が、誰でも簡単かつ正確に行えます。
- 同じ長さの連続カット: ストッパー機能を使えば、同じ長さの部材を何本でも、ミリ単位の狂いなく、かつスピーディーに量産することが可能です。
設置にある程度のスペースが必要なことと、価格が比較的高価な点がデメリットですが、作品の精度に徹底的にこだわりたい方にとっては、最強の武器となるでしょう。
【スライド丸のこ】

集塵機:クリーンで健康的な作業環境の必需品
集塵機は、作業中に発生する木くずや粉塵を発生源で吸引するための強力な掃除機です。
特に室内でDIYを行う場合、その重要性は計り知れません。
- 集塵機のメリット
- 健康維持: 細かい粉塵を吸い込むことは、呼吸器系の疾患につながるリスクがあります。集塵機は、粉塵が空気中に舞い上がる前に吸引し、作業者の健康を守ります。
- 作業効率の向上: 切断時の墨線が木くずで隠れることがなくなり、正確な作業を継続できます。また、作業後の掃除の手間が劇的に削減されます。
- 電動工具との連動: 多くの集塵機には、電動工具のスイッチと連動する機能が備わっています。丸ノコのスイッチを入れると同時に集塵機が作動し、スイッチを切ると少し遅れて停止するため、非常に効率的で無駄がありません。
DIYを長く、そして健康的に楽しむための「環境投資」として、集塵機の導入は非常に価値があると言えます。
一台で活躍する万能電動工具おすすめ

「たくさんの工具を揃えるのは、予算的にも収納スペース的にも難しい」。
そう考えるDIY初心者やライトユーザーにとって、一台で複数の役割をこなす「万能電動工具」は非常に魅力的な選択肢です。
その代表格が、近年急速に普及している「マルチツール」です。
マルチツールは、モーターの回転運動を細かな振動(オシレーション)に変換し、先端に取り付けたアタッチメントを高速で前後させることで様々な作業を行います。
このユニークな仕組みにより、他の工具では真似のできない、かゆいところに手が届く作業を可能にします。
マルチツールならではの得意な作業
- ポケット切断(くり抜き): 壁の石膏ボードや床板の真ん中に、コンセントボックス用の四角い穴を開けるといった「くり抜き作業」が可能です。これは、刃を回転させる丸ノコや、刃を上下させるジグソーでは非常に難しい作業です。
- フラッシュカット(面一切断): 床面から突き出た釘や、壁際に設置された幅木の切断など、障害物に刃が当たらないように「面と平行に」切断する作業が得意です。
- 狭所作業: 手持ち工具が入らないような、狭い隙間や奥まった場所での切断・研磨作業で真価を発揮します。
マルチツール選びのポイント
マルチツールを選ぶ際は、いくつかのポイントを押さえておくと良いでしょう。
- 電源方式: コード式はバッテリー切れの心配なくパワフルに作業できる一方、充電式は取り回しが良く、電源のない場所でも使える手軽さが魅力です。
- ブレード交換方式: 従来は六角レンチなどで固定するタイプが主流でしたが、最近は工具を使わずにワンタッチでブレードを交換できる「ツールレスタイプ」が増えています。作業中に頻繁にアタッチメントを交換する場合、この機能は非常に便利です。
- 振動数の調整機能: 作業内容や材料に合わせて、振動の速さを調整できる機能があると、より繊細な作業が可能になります。
ただし、前述の通りマルチツールは万能である反面、各専門工具のパワーやスピードには及びません。
広範囲の切断や本格的な研磨作業には向いていないことを理解した上で、DIYの「名脇役」として導入すれば、あなたの作業の幅を大きく広げてくれる、頼もしい一台となるはずです。
diy電動工具優先順位に応じた賢い揃え方

- おすすめDIY 電動工具セットの選び方
- 人気のDIY 工具セットマキタ製品
- おしゃれなDIY 工具セット女子向けも
- 購入前に試すDIY 電動工具レンタル
- あなたに合うdiy電動工具の優先順位
おすすめDIY 電動工具セットの選び方

DIYの世界に足を踏み入れる際、必要な基本工具がワンパッケージになった「電動工具セット」は、個別に買い揃える手間が省け、コストパフォーマンスにも優れているため、非常に魅力的な選択肢です。
しかし、内容も価格も千差万別。
ここでは、購入後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、賢いセット選びのポイントを3つの側面から深く掘り下げて解説します。
1. セットの中心となる「核」の工具を見極める
セット商品を選ぶ際、まず最も注目すべきは、そのセットの中心となっている工具、つまり「核」となるドリルドライバーやインパクトドライバーの品質と性能です。
これがDIY作業の基盤となるため、この性能が低いとセット全体の価値が下がってしまいます。
確認すべきは、バッテリーの電圧(V)とトルク(N・m)です。電圧はパワーの源であり、DIY用途では10.8V〜18Vが主流です。
電圧が高いほどパワフルですが、本体は重くなる傾向があります。
トルクはネジを締める力を示し、この数値が大きいほど硬い材料にも対応できます。
自分の作りたいもの(小物か、大型家具か)をイメージし、それに見合ったパワーを持つ工具がセットになっているかを確認しましょう。
2. 将来を見据えた「バッテリーの互換性」
充電式工具のセットを選ぶ上で、見落としがちながら極めて重要なのが「バッテリーの互換性」です。
これは、同じメーカーの同じ電圧のシリーズであれば、一つのバッテリーを複数の工具本体で共有できるというもの。
例えば、最初にドリルドライバーのセットを購入し、後からジグソーが欲しくなったとします。
バッテリーに互換性があれば、ジグソーは「本体のみ」の製品を購入すれば良いため、バッテリーを再度購入する必要がなく、数千円から一万円以上の節約になります。
DIYを長く続けるほど、このメリットは大きくなります。
将来的な拡張性を考え、幅広い製品ラインナップを持つ信頼できるメーカーのシリーズで揃え始めるのが、賢い投資と言えます。
3. 「安物買いの銭失い」を避ける価格と品質のバランス
電動工具セットは1万円以下の非常に安価なものから存在しますが、価格だけで選ぶのは危険です。
極端に安い製品は、モーターの耐久性が低くすぐに壊れてしまったり、バッテリーの持ちが極端に悪く作業にならなかったり、安全機能が不十分であったりする可能性があります。
DIYを安全に楽しむためには、ある程度の品質は担保したいところです。プロ用である必要はありませんが、国内外の有名工具メーカーがDIY向けに展開しているシリーズであれば、品質、性能、安全性の面で安心できます。
目安として、基本的なドリルドライバーとバッテリー、充電器のセットで1.5万円〜3万円程度、複数の工具が含まれるコンボキットであれば3万円〜5万円程度の価格帯が、品質とコストのバランスが取れた選択肢となるでしょう。
人気のDIY 工具セットマキタ製品

電動工具の世界で「マキタ」の名前は、プロフェッショナルな品質と揺るぎない信頼の代名詞です。
その製品は、厳しい建設現場や工房の要求に応えるべく開発されており、その卓越した性能と耐久性は、DIYの領域においても圧倒的な満足感をもたらしてくれます。
初期投資は他のDIY向けメーカーより高くなりますが、それを補って余りある価値と魅力がマキタ製品にはあります。
マキタを選ぶ決定的な理由:強力な製品エコシステム
マキタの最大の強みは、単なる工具の性能だけにとどまりません。
それは、一つのバッテリーを核として広がる、広大な「製品エコシステム」にあります。
例えば、18Vのバッテリー一つあれば、ドリルドライバーや丸ノコといった基本的な電動工具はもちろんのこと、庭の手入れをするための芝刈り機やヘッジトリマー、現場を明るく照らすLEDライト、木くずを吹き飛ばすブロワー、車内清掃に便利なコードレスクリーナー、さらにはキャンプで活躍する扇風機や、現場で一息つくためのコーヒーメーカーまで、数百種類にも及ぶ製品を動かすことができます。
このように、DIYという趣味の枠を超え、生活のあらゆるシーンを豊かにしてくれる拡張性の高さこそ、多くのユーザーがマキタを選ぶ決定的な理由なのです。
DIYユーザーにおすすめのセット
- 初心者向け「10.8V CXTシリーズ」: 軽量・コンパクトで非常に取り回しが良く、女性やDIY初心者でも扱いやすいシリーズです。パワーも家庭でのDIYには十分で、インパクトドライバーやドリルドライバーの基本セットは、最初の一台として最適です。
- 本格派向け「18V LXTシリーズ」: よりパワフルで本格的な作業をこなしたい方向けの、マキタの主力シリーズです。対応する工具の種類が最も豊富で、プロの現場でも使われる高い性能を誇ります。少しずつ工具を増やしていく楽しみも味わえます。
価格の高さやプロ向けのイメージから敬遠されることもありますが、一度手にすればその精度の高さと堅牢性、そして何より作業の快適さに感動するはずです。
「良いものを、長く使う」という価値観を持つ方にとって、マキタは最高のパートナーとなるでしょう。
おしゃれなDIY 工具セット女子向けも

「DIYは男性の趣味」というイメージはもはや過去のもの。
現在では、多くの女性がインテリア作りやリメイクを楽しんでおり、そのニーズに応えるように、電動工具の世界にもデザイン性と使いやすさを両立させた、おしゃれなモデルが続々と登場しています。
重くてゴツゴツした従来の工具のイメージを覆す、女性のDIYライフを華やかに彩る工具セット選びのポイントをご紹介します。
「かわいい」だけじゃない!機能面での配慮
おしゃれな工具セットは、単に見た目の色や形が違うだけではありません。
女性ユーザーが快適に、そして安全に作業できるよう、機能面でも細やかな配慮がなされています。
- 軽量・コンパクト設計: 何よりも重視されているのが、女性でも扱いやすい軽さとサイズ感です。グリップ部分が細く設計されていたり、重心のバランスが工夫されていたりと、小さな手でもしっかりと保持でき、長時間の作業でも疲れにくいよう作られています。
- LEDライト標準装備: ネジを締める場所や切断する線を明るく照らしてくれるLEDライトは、今や多くのモデルで標準装備。室内での細かい作業や、少し暗い場所での作業の精度を格段に向上させてくれます。
- 直感的な操作性: 複雑な設定を必要とせず、スイッチやボタンが少なく、直感的に操作できるシンプルな設計も特徴です。初めて電動工具に触れる方でも、説明書と格闘することなく、すぐに使い始めることができます。
人気のデザイン&カラー
かつての電動工具といえば、緑や青といった無骨なカラーが主流でしたが、現在ではアイリスオーヤマのホワイトシリーズのようなインテリアに馴染むクリーンなデザインや、カインズの「Kumimoku」シリーズに見られるアースカラー(カーキなど)、さらにはアクセントになるピンクやターコイズブルーを採用したモデルも増えています。
作業の合間に部屋に置いてあっても気にならない、むしろインテリアの一部として楽しめるようなデザイン性の高さは、DIYを続けるモチベーションにも繋がります。
工具を選ぶ際は、ぜひスペックだけでなく、「持っていて気分が上がるか」という視点も大切にしてみてください。
購入前に試すDIY 電動工具レンタル

「ウッドデッキを作りたいけど、丸ノコはこのプロジェクトでしか使わないかも」「トリマーに興味があるけど、自分に使いこなせるか不安」。
そんな時、高価な電動工具をいきなり購入するのは大きなリスクを伴います。
そこで非常に有効なのが、必要な時に必要な期間だけ工具を借りられる「レンタルサービス」の活用です。
レンタルが最適な3つのシチュエーション
- 特定の大型プロジェクト: 年に一度の大型DIYなど、使用頻度が極端に限られている工具(例:高圧洗浄機、大型のハンマードリルなど)は、レンタルが最も経済的です。最新の高性能モデルを比較的安価に利用でき、大きなメリットを享受できます。
- 購入候補の比較検討:「マキタのインパクトと、HiKOKIのインパクト、どちらが自分に合っているだろう?」といった購入前の悩みは、実際に両方使ってみるのが解決への一番の近道です。数日間レンタルして、重さ、グリップ感、操作性などをじっくり比較することで、納得のいく一台を選ぶことができます。
- 収納スペースの問題: 特に都市部では、工具の保管場所が悩みの種です。レンタルであれば、使用後に返却するだけなので、収納スペースについて一切気にする必要がありません。
レンタルの利用方法と注意点
利用方法は非常に簡単で、多くのホームセンターが店頭でレンタルサービスを提供しているほか、近年ではオンラインで注文し、自宅まで配送してくれる専門業者も増えています。
ただし、注意点もあります。
DIYを頻繁に行う方にとっては、毎回レンタルするコストが積み重なり、結果的に購入した方が安くなるケースも少なくありません。
また、人気機種は予約が必要だったり、急に使いたいと思ってもすぐに手配できなかったりすることもあります。
自分のDIYスタイル(頻度、作るものの規模)を考え合わせ、「所有するメリット」と「レンタルするメリット」を天秤にかけ、賢く使い分けることが、コストを抑えながらDIYの幅を広げるコツと言えるでしょう。
あなたに合うdiy 電動工具の優先順位

ここまで、DIY電動工具の選び方から揃え方まで、様々な角度から解説してきました。
最後に、あなたが最適な一台を見つけるための、この記事の要点を改めてまとめます。
このリストを参考に、あなただけの優先順位を組み立ててみてください。
- DIYの電動工具は「締める→磨く→切る」の順で揃えるのが基本
- 最初の1台はドリルドライバーかインパクトドライバーがおすすめ
- ドリルドライバーは繊細な力加減が必要な作業に向いている
- インパクトドライバーはパワーが必要な大型の組み立てで活躍する
- 2台目には作品の仕上がりを左右する電動サンダーを検討する
- 切断工具はホームセンターのサービスも活用し、必要に応じて導入する
- 直線切りなら丸ノコ、曲線切りならジグソーが適している
- トリマーは必須ではないが、作品のクオリティを格段に上げる
- 初心者は最初からプロ用ではなくDIY向けのモデルで十分
- バッテリーの互換性を考え、メーカーを揃えると将来的に経済的
- 工具セットは基本工具が含まれ、品質と価格のバランスが良いものを選ぶ
- マキタ製品は高価だが、高い性能と耐久性、拡張性が魅力
- 女性は軽さやデザイン性を重視するとDIYがより楽しくなる
- 高価な工具や使用頻度の低い工具はレンタルで試すのも賢い選択
- 最終的には自分が何を作りたいかで必要な工具の優先順位は変わる